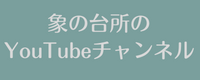私たちが食べたごはんやパン、おかずは、
体の中で少しずつ姿を変えながら「エネルギー(ATP)」へと変換されます。
このエネルギーを作り出す一連の流れを、専門的にはエネルギー代謝と呼びます。
でも、「どこで?」「どうやって?」
と聞かれると、化学式だらけで難しそうに感じますよね。
このシリーズでは、そんなエネルギー代謝の仕組みをキッチンの工程にたとえて3ステップで紹介します。
1️⃣ 解糖系=下ごしらえ
2️⃣ クエン酸回路=煮込み
3️⃣ 電子伝達系=仕上げ
教科書の難しい用語も、料理の風景に置き換えれば一気に親しみやすくなります。
※補足:ここで紹介する「酵素」は、体内で作られる代謝酵素を指します。
市販の「酵素サプリ」や「酵素ドリンク」は、体内酵素と同じ働きをするわけではありません。

エネルギー代謝の全体像
エネルギー代謝とは、
食べた栄養素(主に糖質)が体の中で分解され、
最終的に「ATP(アデノシン三リン酸)」というエネルギー通貨に変わるまでの一連の反応を指します。
その中心となるのが、次の3つの段階です。
- 解糖系(下ごしらえ):糖(グルコース)を切り分け、小さな分子(ピルビン酸)と少量のATPを作る。
- クエン酸回路(煮込み):ピルビン酸を鍋でじっくり煮込むように分解し、NADH・FADH₂という「旨味エキス(電子キャリア)」を抽出。
- 電子伝達系(仕上げ):NADH・FADH₂を使って電子を流し、ATPという完成料理を大量に合成。酸素が仕上げのシェフ役。
第1回:解糖系=下ごしらえの工程
ごはん(グルコース)を包丁で切るように、グルコースをピルビン酸に分解します。
この過程で少量のATPが生まれ、NADHが作られて次の工程へ渡されます。
まさに「下ごしらえ」で、これからの調理(代謝)に使う素材を準備する段階です。
第2回:クエン酸回路=煮込みの工程
下ごしらえした材料(ピルビン酸)を鍋に入れてコトコト煮込むように、
体内ではアセチル-CoAがクエン酸回路に入り、NADHやFADH₂というエネルギーの素を作ります。
同時に二酸化炭素(CO₂)が出ていきますが、これは調理中に立ち上る“湯気”のようなものです。
第3回:電子伝達系=仕上げの工程
煮込みで得た旨味(NADH・FADH₂)を使い、ミトコンドリアの中で仕上げに入ります。
電子の流れでプロトン勾配が作られ、ATP合成酵素(ミキサーのような装置)が回転してATPを合成!
酸素は最後に電子を受け取って水を作る、“シェフの仕上げ”のような大切な役割を担っています。
3ステップのポイント
✅ 解糖系:素早く少量のATPを得る(酸素がなくても進む)
✅ クエン酸回路:NADH・FADH₂などのエネルギー源を作る(ミトコンドリアの中で)
✅ 電子伝達系:電子の流れで大量のATPを合成(酸素が必要)
✅ 全体の流れ:糖 → ピルビン酸 → アセチル-CoA → NADH/FADH₂ → ATP
(=下ごしらえ → 煮込み → 仕上げ)
用語のミニ辞典
- エネルギー代謝:食べた栄養をATPへ変換する体内の化学反応全体。
- 細胞呼吸:エネルギー代謝の中心。解糖系→クエン酸回路→電子伝達系を指す。
- グルコース:ブドウ糖。主なエネルギー源。
- ピルビン酸:解糖系の最終産物。クエン酸回路へ送られる。
- アセチル-CoA:ピルビン酸から変換される分子。クエン酸回路の入り口。
- NADH / FADH₂:電子を運ぶ分子。ATPを作るための“旨味エキス”。
- プロトン勾配:ミトコンドリア内外のH⁺濃度差。ATP合成の動力源。
- ATP:アデノシン三リン酸。細胞が直接使うエネルギー通貨。

まとめ
生化学は、難しい暗記科目ではなく「体の中で毎日行われている料理のようなプロセス」です。
下ごしらえ(解糖系)→ 煮込み(クエン酸回路)→ 仕上げ(電子伝達系)という流れをイメージすれば、
エネルギー代謝の全体像がぐっと身近に感じられます。
下記で、それぞれの工程を詳しく見ていきましょう(各ブログに飛びます)